社会人・既卒者向け!公務員転職ガイダンス
社会人・既卒者向け!公務員転職ガイダンス
既卒者がEYEを選ぶ3つの理由
公務員を目指すにあたって、既卒だから不安にしていることを解消するために、今回のアドバイスを役立ててください。
1.記憶に残っている6名の合格者の紹介
2.公務員試験の概要と効率よい勉強法
3.多くの科目をやり遂げるための時間の作り方
4.今からできる面接対策
社会人・フリーター転職成功!公務員合格体験記

人生の分岐点
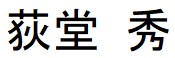
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類、国家一般職
一度諦めた公務員に再度挑戦したい
特別区を志望した理由は、特別区が、基礎自治体の中でも人口規模が約950万人と非常に大きく、多種多様な人種が存在するため、特別区の抱える課題を解決できれば、日本社会全体を良くしていくことができると考えたからです。
また、大学卒業後は民間企業の道へと進みましたが、一度諦めた公務員になりたいという夢にサイド挑戦したいと思ったからです。
兄弟からの紹介がきっかけだった
兄弟からの紹介がきっかけでした。公務員予備校を探すに際し、大手と言われる予備校の説明会にも参加し、そこでは規模が大きく情報量が多く授業の質も高いなと感じた反面、普段の相談や小論文・面接対策においては力を入れていないように感じました。一方EYEでは、小規模ではあるものの、個別相談や小論文の添削などが手厚く、ここならどんなことでもそうしやすそうだなと感じたため、入学することに決めました(実際、普段の何気ない事にも相談に乗ってくれました笑)。
担任や科目の先生に気軽に相談や質問ができる
担任の岡田先生や科目の先生に気軽に相談や質問ができるところです。主要な授業科目の先生は、授業終わりや休み時間、授業前の空き時間であれば質問ができる環境にあったため、分からないところはすぐに解決できたのが良かったです。また担任との個別相談では、面接対策や小論文についてもかなり細かく相談できたため、筆記試験以外の対策の時には非常に助かりました。
アルバイトと試験対策を両立させた
アルバイトと試験対策を両立させた事です。民間企業を退職したタイミングが悪く、1年目の試験を受けた際には勉強が追いつかず良い結果を残すことができませんでした。その後アルバイトを始めた時には、授業の進捗状況を岡田先の先生と毎週確認しながら、アルバイト始業前や終わりに塾の自習室を活用し、とにかく勉強時間を確保し、先生と二人三脚で合格を目指した事が結果に繋がったと思っています。
社会人としての経験は面接でのアピールポイントにもなる
公務員試験は、やればやった分だけ合格に近づきます。民間企業と違い、学歴が高いからと言って合格するとも限りません。特に大学生の方は、周りが民間企業への就職が決まった中もずっと勉強しているのは辛いとは思いますが、諦めずに最後まで試験対策を積み重ねて行けば、自分の夢を叶えられると信じています。また、既卒の方も、既卒だから試験に不利という事もありません。例え、仕事を少ししか経験していないとしても、社会人としての経験は学生時代には絶対に得られません。逆に面接ではアピールポイントにもなりますので、是非その経験をアドバンテージと捉えて、夢に向かって頑張ってください。

既卒でも大丈夫!何歳からでも遅くない!
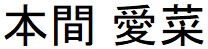
- 最終合格
- 川越市(大学)、千葉県上級
公務員の家族を見て興味を持つように
私の家族が公務員として働いていたことから、公務員の仕事に興味を持ちました。年齢的に難しいのではと思っていましたが、調べていくうちに受験可能であることが分かり、挑戦することを決めました。また、前職では様々な職種を経験していました。その中で、人と関わる仕事をしていたこともあり、広い分野から人々の生活を支える仕事がしたいと思ったからです。
公務員試験について一から教えて下さった
いくつかの予備校の個別相談に行った中で、EYEは公務員試験についてほとんど知識がない私に対して、親切に一から教えて下さったことが印象に残り、入学を決めました。また、アットホームな雰囲気であるため相談がしやすいことや、既卒生との交流の場が多くあることに魅力的に感じました。そのほかには、広い自習室も完備されていたことも決め手の一つです。
すぐに相談できる環境があったことがよかった
EYEはアットホームな予備校なので、すぐに相談できる環境があったことがよかったです。各校舎に担任の先生がおり、気軽に相談することができたことでモチベーションの維持にも繋がりました。また、受験仲間を作るイベントが開催されている点もすごく良かったです。そのほかには、WEB動画で受講できたことで、場所や時間帯に関係なく学習に取り組めたことも良かったです。
面接カードは個別相談を利用
面接対策は、筆記試験が終了後に本格的に取り掛かりました。面接対策の授業に参加することで、面接に関する情報収集していました。また、受講生同士で想定質問の作成を行ったりしていました。面接カードについては、個別相談を利用して、丁寧に添削していただきました。論文対策は、吉井先生の論文講座で受講した参考答案を土台として一部、自分の言葉に変えて書きやすい様に修正して、1日1テーマを目標に暗記をしていました。また、模試に出たテーマについても暗記するようにしていました。
周りの人と比べすぎずに自分のペースで
公務員試験に臨むことは、かなり悩んだ上で覚悟を決めて決断したつもりでしたが、年齢のことを考えると焦りを感じたり、落ち込んだりすることもありました。試験の度に全部不合格だったらどうしようと不安にもなりました。それでも、自分を信じて突き進み、最終的に合格をつかみ取ることができました。何方も、周りの人と自分を比べすぎずに自分のペースで最後まで頑張ってほしいと思います。不安に押しつぶされそうになっている人もいると思いますが、過ぎたことや終わったことはいったん忘れて、もう一度気持ちを切り替えて頑張りましょう!そして、たまには自分を沢山褒めてあげてください!応援してます!

大事なのは笑顔!!
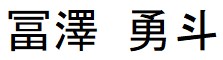
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類、東京消防庁消防官Ⅰ類
公務員の父の姿をずっと見てきたから
一番の理由は、父が公務員で父の姿をずっと見てきたからです。また大学のアルバイトでイベントスタッフに携わり、地域の人々と近くで関われる公務員という仕事に興味を持ち、公務員になろうと決めました。もう一つの理由は、あまり大きな声で言えないですが、安定した職業だと言うことです。私自身、一攫千金を狙うタイプではなく、コツコツ地道に働きたいと思っていたので、そのスタンスも公務員にマッチしていました。
岡田先生が直接説明してくださったから
EYEに決めた理由は、いろいろな予備校に説明を受けに行った中で、EYEだけ唯一、岡田先生が直接説明をしてくださったからです。民間企業で働きながら公務員試験の勉強をしなければいけない状況のなか、まだ入学するかも決めていない私に講師自ら説明をしてくださったことにとても温かみを感じました。他の予備校だと受付の方による説明がほとんどだったため、EYEと比較したときにEYEなら親身になって教えてくれそうだと感じ。EYEに決めました。
LINEでいつでも相談できる
どんなこともLINEでいつでも質問できることが私にとって大きかったと思います。入校したのが遅く他の皆よりスタートが遅かった私にとって、どんな小さな不安も先生にぶつけることができたことが合格につながったと思います。先生もそんな私の質問に真摯に応えてくださいました。個別相談もLINEで行えて、民間企業で働いている私にとってとても助かりました。
面接で緊張しないようにする
工夫したことは、面接で緊張しないようにすることです。私は過去の受験で、面接中に緊張して声が小さくなって尻すぼみになることが欠点だと分析しました。それを克服するために、現職で上司の方に積極的に話しかけて自分の意見を伝えるように心掛けました。このように面接の状況と同じような状況に自分を追い込むことで場慣れの下地ができ、本番では緊張することなく素の表情を出すことができたと思います。
多少遠回りしても大丈夫
これから合格を目指す皆さん、現在は授業に参加しつつ問題集を解きまくっていると思います。皆さんのその努力は必ず実を結びます!途中は逃げ出したくなったり、突然焦ったりする時期があると思います。ですが、今まで続けてきた努力が無くなることは決してありません!私は既卒で働きながらの受験となりましたが、無事合格することができています。多少遠回りしても全然大丈夫です。リラックスして、自分のペースで頑張ってください!良い結果がでるよう応援しています。

諦めなければ勝つ!高卒でも大丈夫!!

- 最終合格
- 大網白里市(上級)
安定とやりがいを両立させることができる
元々前職が消防士ということもあって、市役所の業務に興味がありました。また、人と関わることが好きでなるべく地域の方と距離の近い市役所の職員になりたいと思うようになりました。また私が以前、消防士として働き始めた年に、新型コロナウイルスが流行し様々な予想外なことが起こりました。周りや両親がボーナスカットされている中、公務員である私はボーナスが満額出たり、コロナウイルスに罹患してしまった時も特別休暇で年次休暇を使用せずに休むことができました。地域貢献などのやりがいと世の中の出来事に左右されず安定した仕事を両立させたいという安定志向の私にとって、公務員という職業はとても魅力的だと感じ、退職を決断した時も次も絶対に公務員が良いと強く思いました。
受験生のサポートの手厚さ、意思の尊重
予備校選びで迷っていたところ、もうすでにEYEに通っていた妹から紹介されて実際に説明を受けに行きました。他の予備校も何校か説明を受けに行っていたのですが、他の予備校に比べ、受験生との距離が近くサポートも充実しており、困った時にすぐに助けを求められそうだと思い決めました。また、他の予備校とも迷っていると伝えたときも「EYEが良いよ。」押すのではなく、「重要だから色々と見ることは大切です。」と受験生の意思を尊重してくれるような対応も決め手でした。面接対策で、担任の先生と何度も練習することができ、面接指導に長けている方々だということも非常に重要なポイントでした。
最後まで面倒を見てくれる面倒見の良さ
私は大学に行ってないため、公務員試験の情報などを入手する機会が少なかったり試験仲間がいなかったため、よく法島先生に個別相談やLINEを使って相談していました。特にLINEは予約などが不要で気軽に質問することができたためとても助かりました。EYEの契約は9月末で終わりでしたが、私はC日程まで受験していたため、年末まで担任の先生のサポートを受けることができてとても心強かったです。こうした生徒との距離が近く、最後の試験が終わるまでサポートしてくれる面倒見の良さには本当に救われました。また、既卒ゼミなど合格者の方と交流できたり連絡先をもらうことができ、実際の経験に基づいた様々なアドバイスは大きな力になりました。こうした繋がりの多さは、元々試験仲間がいなかった私にとって、EYEで学習して良かったと強く感じました。
1日どれだけできるかよりもどれだけ継続できるか
・勉強について
私は公務員試験においては、1日の勉強量よりも試験まで勉強を続ける継続力の方が大切だと思います。一見、当たり前じゃんと思うかもしれませんが、公務員試験は長いため意外と難しくモチベーションがなくなってしまったり、不安になって精神的に滅入ってしまうパターンも少なくありません。そのため、焦って無理をして勉強するよりも自分ができる量を継続することのほうが大切だと思います。
・面接について
面接対策では、最初に基本的な受け答えを反復練習して(志望動機などは担任の先生に相談しつつ、自分らしさを加えると良いものができると思います。)、あとはとにかく自治体のことを知ることを行いました。自治体の取り組みや特徴を知ることで、面接の要所要所で自治体への思いをアピールすることができるからです。あとは、はっきりと受け答えをすることはとても重要だと思います。面接の雰囲気に呑まれて縮こまってしまうこともありますので、そこでもはっきりとできる自信と度胸は面接には欠かせないと思います。
1人で抱え込まずに周りを頼る
公務員試験は自分との戦いでもありますが、1人で全て解決することはとても難しいです。EYEは担任の先生や講師の方に相談しやすい環境であり、受験仲間や合格者の方と交流をとりやすい環境であると思います。そのため、困ったときや悩んだ時には周りを頼ることが大切です。こんなくだらないことで良いのかな、、。と迷う時もあります。しかし、大切なのは自分が追い込まれて潰れる前に対処することですので、遠慮なく頼って良いと思います。公務員試験は、周りに助けてもらったりすることのありがたさや重要性を学べる良い機会でもあると思います。公務員試験はとても長く、試験などで辛いこともたくさんあると思います。ですが、それを乗り越えた先に大きなものを得ることができます、諦めずに続けた先に合格があります。自分を信じて自分と向き合い、頑張ってください。応援しています!
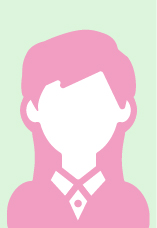
10月からでも合格出来ます!
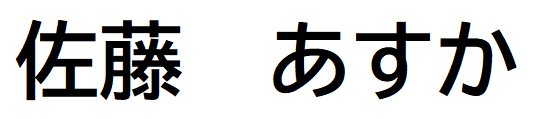
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類、八潮市(大卒)
より幅広い面から人々の役に立つ仕事をしたいと思ったから
1点目は民間2社を経験し、より幅広い面から人々の役に立つ仕事をしたいと思ったからです。そして2点目は学生時代に学んでいた観光・地域振興の分野に携わりたいと思ったからです。以上の理由から転職先として様々な仕事を見ていく中で、公務員なら自分のやりたいことが出来るかもしれないと感じ、公務員を志望しました。
EYEは相談しやすい環境があった
私がEYEに入学した理由は、各校舎に担任の先生がおり、相談体制が整っていると感じたからです。EYEに入学するまでに様々な予備校を見学しましたが、2つ以上の校舎を掛け持ちで担任していたり、個別授業の枠が生徒の数に対して少なく、いざという時に相談しにくいという予備校もありました。それに対しEYEでは各校舎に1人ずつ担任の先生がおり、個別授業についても対応してくださる先生が沢山いるという事で、いざという時にすぐ相談しやすいということでEYEを選びました。
困った時にすぐに相談できる
勉強で躓いた時などに、すぐ相談できる環境があるのはとても良かったです。担任・副担任の先生や個別相談で対応してくださる先生方に加えてチューターの方々もいるため、困った時にすぐ相談出来ますし、相談先もその時の自分の状況に応じて選べる事が多かったように思います。特にチューターの方々は公務員試験に合格している人達であり、実際に使用していた教材や勉強方法などをアドバイスして貰えたのでとても参考になりました。
苦手な所はなるべく早い段階で解決するようにしていた
私は勉強を始めた時期が他の人よりも遅かったため、講義動画を見る時は常に倍速で視聴していました。また分からない所や苦手な所はそのままにしたりせず、なるべく早い段階で解決するようにしていました。論文、面接の対策としては、論文の模範解答や自分の志望動機などを大きめの紙に書き出し、毎日家で音読をしていました。予備校までの通学中には自分の声で録音したものを聞き、内容を暗記をしていました。また面接対策としては、聞かれそうな質問とそれに対する自分の答え方を纏めておきました。そして同時進行で、他の生徒の方との面接練習をひたすら行いました。
自分に合ったやり方を
私は学生時代ずっと文系で、公務員試験勉強を始めた頃は苦手科目ばかりでした。しかし分からない所は分かるようになるまで何度も質問をし、自分でも繰り返し解いていくことで、次第に解けるようになり苦手意識も少なくなっていきました。悩んだ時には先生やチューターの方々に積極的に相談し、自分に合ったやり方を見つけてみてください。また、皆さんの中には私のように遅い時期に勉強を始めた方もいると思います。周りの人の中には講義視聴が終盤に入っていたり、視聴が終わって問題集に取り掛かり始めてる人も出てきて、焦ったりしてしまうこともあると思いますが自分のペースを大切にしながら勉強に取り組んでいってください。
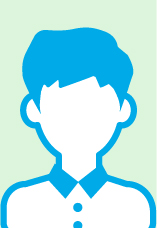
短期集中合格
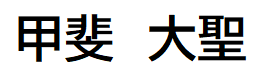
- 最終合格
- 東京消防庁消防官Ⅰ類
専門性を高めつつ、人の役に立ちたい
専門性を高めつつ、人の役に立ちたいという思いから、公務員を目指しました。元々私は、資格試験の合格を目指し、勉強をしていました。しかし残念ながら合格できず、その後の進路をどうしようかと悩んでいました。そんな時、ふと幼い頃夢だった消防官を思い出しました。専門性を身につけて社会に役立てたいという軸を持っていた私は、災害知識を駆使し、人命を助ける消防官も良いのではないかと考えました。せっかくだから消防官も進路に入れて考えてみようと思ったことが、今回公務員を目指すきっかけでした。
EYEの雰囲気が良く、相談しやすい環境だと思ったから
EYEを選んだ理由は2つです。一つは、EYEの雰囲気が他の予備校よりも良いと感じ、相談しやすい環境だと思ったからです。EYEでは、科目質問というサービスがあり、時間が合えばいつでも先生に相談できたり、論文添削などしていただけます。そのような点にも惹かれました。
もう一つは、価格が他の予備校よりリーズナブルであるということです。資格試験の勉強にお金を費やしていた私にとって、EYEが一番お手頃な価格で勉強ができると思いました。
すぐ予約できる科目質問で、論文を添削していただけたことが良かった
EYEで学習して良かったことは、やはり科目質問です。残り少ない期間の中で、自分が最も伸びる科目は、論文だと考えました。そんな中、先生をすぐ予約でき、いつでも添削していただける環境は、とても良かったです。さらに自分の校舎以外の校舎の先生を予約できる点も、時間がない私にとって、ありがたいと感じました。また、勉強の仕方やスケジュールについては、担任の先生にいつでも相談できるところも良かったです。
とにかく経験を積む
勉強で工夫したことは、とにかく経験を積むことです。特に論文は、人に見てもらうことで、伸びる科目だと思います。そのため、書いたらすぐ先生に見てもらうなど、経験を積むようにしました。また、面接対策についても同様です。練習せずに本番を迎えてしまうと、意外と言いたいことが言えない状況になってしまう恐れがあります。そのため、科目質問や模擬面接を積極的に活用して、本番を迎えるようにしました。
受験勉強をやってきて良かったと思える日が来る
試験に合格するまでは、日々不安に感じると思います。周りが就職を決めていく中、公務員受験者は、夏まで頑張らなければいけません。しかし、受験まで一生懸命に取り組むことができれば、必ず自分の行きたいところに合格することができます。合格した後は、受験勉強をやってきて良かったと思える日が来ると思います。最後まで諦めずに頑張ってください。
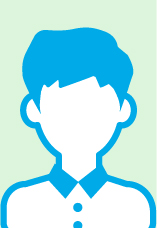
たくさん頼りましょう
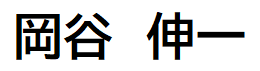
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類
安定していて、定時に帰れそうというイメージがあったから
私が公務員を志望したのは、安定していて、定時に帰れそうというイメージがあったから です。自分が大学生の時にも、公務員になりたいと思っていたのですが、独学で勉強が続 かなかったこともあり、大学4年生の時には、公務員試験を受けるのを諦め、民間企業で の就職活動を1年間していました。しかし、就職活動をする中、やはり公務員の方が自分が受けていた民間企業よりも福利厚生や給与などの条件がいいと思い、大学を卒業した年に無職になることを決め、公務員試験の勉強を始めました。
サポートが他の大手の予備校と比べて手厚いと感じたから
私がEYEに入学した理由は、受験生をサポートしてくれる制度が他の大手の予備校と比べて手厚いと感じたからです。実際、法島先生や岡田先生などの先生は何度も無料で相談に乗ってくれました。また、ひと月に何度か無料で各科目の先生たちに直接無料で質問できたのもよかったなと感じました。勉強している科目でわからないことがあったときにはすぐその科目の先生に質問するようにした結果、勉強で困ることが少なくなりました。
自習室が月から土曜の毎日に開放してくれていた
EYEで学習してよかったことは、自習室が月から土曜の毎日に開放してくれていたことです。私は家で勉強することが苦手で、どうしてもなまけてしまう傾向がありました。そこで、毎日EYEの自習室に通うことによって、勉強を続けることができたので、よかったです。また、EYEではイベントなどで受験仲間つくる機械を提供してくれた点もよかったです。受験仲間がいたおかげで、勉強のモチベーションがアップし、勉強をつづけやすくなったので、とても感謝しています。
同じ問題集を何度も解いた
私が勉強で工夫したことは、同じ問題集を何度も解くということです。いろいろな問題集 にむやみに手を出すのではなく、一科目につき問題集は基本的に1冊と決め、その問題集を何度も繰り返すようにしていました。何度も同じ問題集を繰り返すことにより、だんだん問題を解くスピードがあがったり、問題の解法を身につけやすくなったりし、知識の基礎が定着しやすくなったように感じました。
困ったことがあったらすぎに先生方に相談する
公務員試験の勉強や面接対策はやればやるほど努力が実りやすくなると思います。勉強を 長く続けることは大変ですが、EYEでは勉強が続けやすくなるサポートをしてくれます。 困ったことなどがあったとときは、自分ひとりで悩むのではなく、すぐに先生方に相談す るのがいいと思います。EYEでは、先生方が親身に勉強の相談などにのってくれるので、 それを利用するのが、合格への近道だと思います。皆さんの努力が実り、志望先に合格す ることを願っています。頑張ってください。
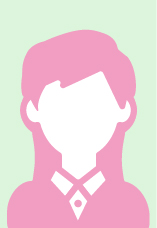
既卒でも大丈夫!短期生でも大丈夫!
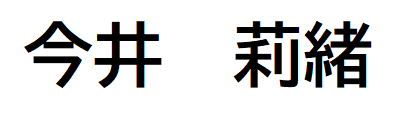
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類、横浜市(大学卒業程度)、国立大学法人等職員
公務員は幅広い仕事を経験できて働きやすい環境が整っている
キャリアを長く続けたいと思っているため、幅広い仕事を経験できて働きやすい環境が整っている公務員を志望しました。新卒で民間企業に就職しましたが、やはり民間では定年までに経験できる職務の内容が限られていると感じました。私は好奇心旺盛な性格で様々な政策に興味があったので、ジョブローテーションができる公務員に大変魅力を感じました。また、姉が特別区の公務員で、労働条件や給与の話も聞いていたので、労働環境がより整っている公務員を志望しました。
岡田先生が面談で最初から丁寧に説明してくださった
母親がネットで見つけてくれて、アットホームで面倒見がよいという言葉に惹かれ、お話を聞きに行きました。最初に岡田先生と面談した時は、公務員試験のことは全く分からない状態でしたが、最初から丁寧に説明してくださり、大変ありがたかったのを覚えています。LINEでも相談できたり、自習環境も整っているところに魅力を感じ、入会を決めました。
自治体の説明会や既卒ゼミ、集団討論練習会などのイベントが充実していた
まずは、自習環境が整っていたところがよかったです。私は12月末に前職を退職してから本格的に勉強を始めたので、一日中籠れる場所があったことがとても助かりました。また、岡田先生がどの授業をいつまでに視聴したらよいか、ペース配分を考えてくださったのもありがたかったです。
そして、自治体の説明会や既卒ゼミ、集団討論練習会などのイベントが充実していたこともEYEに入ってよかったと思う理由の一つです。
一緒に働きたいと思ってもらえるように、明るく柔らかい印象を残すことを心がけた
私は10月末に入学しましたが、12月末に前職を退職するまでは、授業のアーカイブをいくつかしか見れず、1月以降から本格的に勉強を始めたので、とにかく時間がありませんでした。そのため、苦手科目の克服に時間をかけるよりも、得意な科目で点数を落とさないように意識して勉強していました。特に苦手だったミクロマクロは、理解できた基礎の部分だけ解けるようにし、逆に頭に入ってきやすかった憲法民法は何度も復習していました。
面接対策は、特別区の面接アドバイス会で出会った既卒の友人達と練習したのと、仕事センターを活用しました。面接で意識したことは、エピソードの中になるべく前職の職務のことを盛り込むようにし、私が職員として働いているところを具体的にイメージしてもらえる内容を伝えるということです。あとは、一緒に働きたいと思ってもらえるように、明るく柔らかい印象を残すことを心がけていました。
社会人経験があってよかった!
私は、最初、新卒に比べて既卒は不利だと思っていました。しかし、実際は働いていた経験が面接でとても役に立ったので、社会人経験があってよかったと思いました!もちろん、新卒の方も学生時代に自分だからできたことが必ずあるはずなので、そこを目一杯アピールしてください!合格できるか不安になることもありましたが、悩むよりもやるべきことをやるしかありません。たった5分でも10分でも、勉強した分だけ合格に近づくと思って、前向きに頑張ってください!
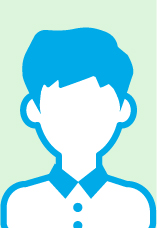
運だけは良い奴の体験記
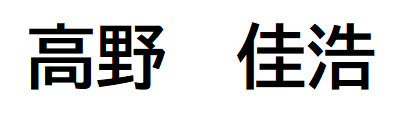
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類
半年から1年程度で合格できることや社会的信用が高いことから
前職の職場で、同期の残業代踏み倒しや男性上司を見て勤めていた会社に将来性を全く感じなく、この会社に所属し続けるのは、リスクと考え、転職を決意。しかし、何の能力も資格も無い状態であり、転職も難しい状態でした。
そんなある日、前職の同期の1人が国立大学職員の合格を聞き、公務員転職の存在を知りました。その際に、インターネットで公務員試験を検索し、半年から1年程度で合格できることや社会的信用が高いことから公務員試験に挑戦を決めました。
費用が少し安かったEYEを第一候補に考えた
まず公務員試験を考えた時に独学でも合格可能な記事はたくさん見ましたが、私自身商業高校卒業で、普通科の勉強はほとんど行っておらず、大学受験も指定校だったので独学は無理と判断。また社会人で、金はあったので少しでも楽できるよう予備校に通うことにしました。
インターネットで検索し、候補先としてEYEや資格取得の大手2社から資料請求した所、費用が少し安かったEYEを第一候補に考えました。次に、実際に面談をした時に某予備校の人が明らかに上から目線で、お高く止まってんじゃねぇよと思いEYEに決定しました。
面談である程度の道筋を作ってくれていたことで余計なことをせずに済んだ
まず何をすれば良いかわからなかったので、面談である程度の道筋を作ってくれていたことで余計なことをせずに済みました。
経済学は岩城先生が私には合っていて、とてもわかりやすかったです。
法学の紺野先生は授業の合間に軽い雑談があり、3時間の授業を飽きさせず聴くことができました。
論文や面接カード・面接の情報など過去のデータがたくさんあったので、どうすれば良いのか学べました。
どんな自分だったら相手は私を買いたくなるのかを常に意識していた
私は5月に入校していましたが、仕事をしていることを言い訳に勉強をしていませんでした。これではいけないと思い退職し、本格的に始めたのは11月からです。おそらくみんな悩む数的処理について書いておきます。ちなみに、ちゃんと時間かければできるみたいですね。私はまず始めた時に1ミリもわかりませんでした。そこで初歩の初歩の参考書から勉強を始めましたがそれもわからず、普通にモチベーション下がるだけで諦めました。最終的には数的推理は捨て、判断推理を基本的な問題は取れる程度までしかやってません。公務員試験は1/5なので運頼みも工夫なのかもしれません。
面接対策の工夫について、私は面接なんて最終的には運でしかないと思っています。ですが、運を自分の方向に少しでも向けることはできるのかなと思います。私がした工夫は意識だけです。意識したのは、どんな自分だったら相手は私を買いたくなるのかを常に意識してました。
ちゃんと勉強と面接対策した方が、合格した合格した時の喜びも大きいはず
タイトルの運だけは良いやつのことについて書いておきます。これをマネしなければ、合格できるかもしれません。
まず、筆記試験のためにおおよそ他の人は2〜4月に日に平均10時間は勉強しますが、私の2〜4月の日の平均勉強時間は15分切ってると思います。その結果半分ギリギリいかないくらいの点数です。
また私の第一志望の特別区は、論文試験のウエイトが重いとのことでした。金払って授業は聞きましたが、練習したのは模試の一回です。(ここでそこそこ点数取れたのがダメだった)
その結果、1000字以上書く試験で1000字を少し超えるだけの論文を書きました。普通じゃありえません。
その結果、運良く今年の一次試験の倍率が低かったこともあり、一次試験に合格しました。
二次試験の面接は、既卒同士で繋がれる機会があり、そこのメンバー同士で少し練習しました。面接の頻出の問いについては、3分間プレゼンテーションだけは完璧にしました。他の問いについては、別に会話するだけなのに考えるだけ時間の無駄では?と思い、何も用意しませんでした。前後の会話の一貫性だけはあるように話すことだけは、注意しました。
今回たまたま合格という結果になりましたが、こんなんで普通受かる訳ありません。
誰に金出してもらうかわかりませんが、落ちたら金をドブに捨てるのと一緒です。また、無職になるか、9月まで採用活動をしなければいけないような売れ残り企業に就職することになるかもしれません。ちゃんと勉強と面接対策しましょう。きっと、その方が合格した時の喜びも大きいはずです。

3度目の挑戦
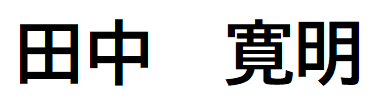
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類(電気)
一番は公務員の安定性に惹かれたから
一番は公務員の安定性に惹かれたからです。私は新卒で民間企業に入社し、その後色々とあって仕事を辞め一年程度フリーターをしていました。その際に感じたこととして若いうちはアルバイトでも生計を立てていくことは可能ですが、年をとって体調不良が多くなってきた際に今のままでは生きていくのは難しいということです。そこで公務員の安定性に惹かれて公務員を目指すことを決めました。
面接対策に力を入れ、一人一人にしっかりと対応してくれると聞いたから
面接対策に力を入れている事、そして少人数制を取っているので一人一人にしっかりと対応してくれるという口コミを聞いたからです。私はコミュニケーションに不安を抱えており、実際過去2年特別区を受けていますが、落とされたのは全て面接でした。そのように自分の欠点がはっきりしていたからこそ、そこを鍛えることができるEYEを選びました。
定期的に個別相談を活用することで有益な情報が得られた
私がEYEで学習してよかったことは3つあります。1つ目は効率的な勉強方法を学べたことです。今まで私は「1ヶ月まとめて一つの科目を勉強して、次の月には別の科目を進める」といった勉強の仕方をしていましたが、公務員試験の科目は非常に多いため、このやり方だと最後の方になってくると最初に勉強した内容を忘れてしまいます。だからこそ全ての科目を少しづつ進めるという勉強方法を学べたのは大きかったです。2つ目は面接対策が充実していたことです。講師との練習があることはもちろんとして、筆記試験合格後のイベントでコミュニティが形成されるので、そのコミュニティを活用することでかなりの数の実践経験が積めたのが良かったです。最後は情報面です。前述した勉強のやり方などはもちろん、自治体毎の例年の試験内容やその変化など、定期的に個別相談を活用することで有益な情報が得られたことが良かった点です。
一つ一つ段階を踏んで出来ることを増やしていく
私は面接対策で3つの段階を踏みました。1つ目は話す内容を事前に用意しておくことです。私はあまり頭の回転が早い方ではないので、自分の中に解答がない質問にとっさに良い返答をすることができません。だからこそされる可能性が高い質問については事前に解答を用意してました。2つ目は用意した内容を何も見ずに話せるように暗記しました。その際に気を付ける事としては一字一句覚えようとするのではなく、主旨を覚えるようにして細かい言い方などはあまり意識しないようにしてました。そこまで覚えようとすると情報量が多くなりすぎるのと、状況に応じた融通が効きづらくなるからです。そしてそこまで問題なくこなせるようになったら最後の段階として、印象の良い話し方ができるように面接練習をひたすら繰り返すことです。意見を貰う際も人によって感じ方は違うので、なるべく多くの方に見てもらうことを意識しました。全体の総括としては、一気に全てのことをこなすのは難しいので一つ一つ段階を踏んで出来ることを増やしていくことが良いと思います。
しっかりと対策をすれば受かる試験
私が受験したのは特別区と国家一般ですが、その範囲においては、公務員試験は既卒で職歴に空白があって尚且つコミュ障だったとしても、しっかりと対策をすれば受かる試験です。ただどうしても長期戦になりますので、しっかりと計画性を持って、あまり無理をせず適度に息抜きをしながら頑張るのが大切だと考えます。体調にも気を使って頑張ってください!
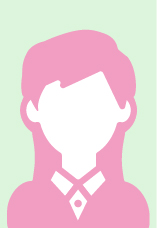
既卒でも合格!
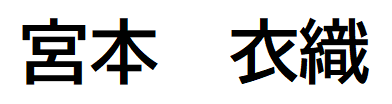
- 最終合格
- 東京都Ⅰ類B(一般方式)、国家一般職
公務員のほうが自分の性格に合っていると感じたから
私が公務員を志望したきっかけは、結果を追い求める企業で働く自分の姿が想像できず、公務員のほうが自分の性格に合っていると感じたからです。人生の3分の1以上を働いて過ごすのかと思った時に、自分にとってのストレスが少ない環境で仕事がしたいと思い、公務員を目指しました。また、志望動機を考える中で、幅広い分野から政策の実行やセーフティーネットを充実させることで、国民・市民が安心して暮らせるようサポートする点に魅力を感じ、志望しました。
LINEで気軽に相談や面接対策ができ、手厚いサポートに魅力を感じた
まず、私は大勢がいる教室で授業を受けたり、自分のペースで勉強できない環境が苦手だったので、オンラインで受講できる所を探していました。そこで、EYEを見つけ調べていく中で、オンライン受講は孤独になりがちですが、LINEで気軽に相談や面接対策ができ、手厚くサポートしていただける点に魅力を感じ、入学を決めました。また、EYEは他の予備校と比べて少し安く受講できるので、入学しました。
計画的に学習できた点がよかった
オンライン受講でも、孤独にならず、担任の法島先生に常にLINEで相談しながら勉強することができたので、計画的に学習できた点がよかったです。また、個人的に私は法学部ではないので法律の知識がゼロでしたが、憲法の授業がすごくわかりやすく、得意科目として実際試験でも点を取ることができた点がよかったです。加えて、オンライン受講でも、各自治体の説明会に参加できたり、面接・論文添削もしていただけたので、サポートが充実していてよかったです。
どれだけ解けない問題を減らすかを意識していた
まず、担任の法島先生のアドバイス通り、他の教材に手を出さず、ひたすらダーウィン(問題集)と過去問を解いて勉強しました。特に、数的処理とミクロ・マクロが苦手だったので、ダーウィンと過去問を10周以上し、解けない問題のページを破って独自に冊子を作ったりして勉強しました。勉強時間も大事ですが、どれだけ解けない問題を減らすかを意識していました。また、面接対策では、Wordに想定質問に対する回答を全て書き出して、自分なりの言葉で短くしゃべれるように録音機能やLINE通話を使って練習しました。
周りを頼りながら自分のペースで頑張ってください
まずは、ここまで読んでいただきありがとうございます。公務員試験は、長丁場で最終合格が分かる時期も早くて7月以降なので、民間就活をしている友達を見て不安になることがあると思います。ですが、いつ内定をもらっても働き始める時期は同じなので、自分を信じて最後まであきらめずに頑張ってください。また、私自身、モチベーションが下がって全然勉強をせずだらけてしまった時期もありましたが、担任の先生や周りに相談したりすることで、最後には合格することができました。公務員試験は、マラソンなので、周りを頼りながら自分のペースで頑張ってください。陰ながら応援しています!
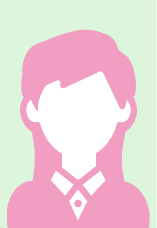
私でもどうにかなりました!
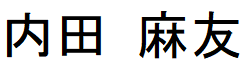
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類、国家一般職、国税専門官
行政の公務員として友人たちが生き生きと働いているのを知り、目指し始めた
もともと公務員系の別の仕事をしていたのですが、職場環境や自分のやりたいことが変わっていく中、行政の公務員として働く友人たちが生き生きと働いているのを知り、目指し始めました。民間への転職も考えましたが、今の日本では公務員の身分が依然強いので、そこもポイントでした。あとは、都内出身でないので、東京の中心での勤務に憧れがありました。大変不純ですね…。
どの予備校よりも面倒見が良さそうだと感じたから
どの予備校よりも面倒見が良さそうだと感じたからです。私が法島先生に入塾相談をしたのは11月の終わりだったのですが、今からでも間に合うのか不安だった中、私の事情を聞いた上で背中を強く押していただけたことが決め手でした。また、仕事をしており時間がなく、かつ公務員試験に関しても無知だった私にとって、オンラインを活用し面接練習や相談がいつでもできるのも魅力的でした。
定期的に学習の仕方や不安なことを質問できる環境にあった
結果的に筆記は高得点で全勝しました。国家一般職に関しては9割得点しています。これは、EYEの講師の方のレベルの高い授業と、ダーウインのおかげだと思っています。特に私は文章理解と民法以外はダーウインしか使いませんでした。よい講師、テキストを恵んでくれたのが、EYEで学んでよかったことの一つです。
もう一つは、定期的に学習の仕方や不安なことを質問できる環境にあったことです。法島先生には週間学習表をふまえてのアドバイスや、メンタル面での支えを多くいただきました。この点はとても強かったと思います。
一つのテキストを繰り返すことで知識を定着させることができた
私は正規で働いているという条件だったにも関わらず、公務員試験の勉強を始めたのが12月の頭、そして年明けの試験を受けようとしているという大変無謀な挑戦をしていました。(結果的に3月で退職しましたが)そんな中意識していたのは、一つのテキストを繰り返すということです。繰り返すことで知識を定着させることができました。特に直前期は焦り、他のテキストに手を出したくもなりましたが、結果的に一つのテキストを極めたことが高得点につながったと思っています。
毎日少しずつでも学習を進めてば未来は開けるはず
これを読んでいる方はおそらく公務員試験に臨むか悩んでいる方、または試験が迫りナイーブになっている方だと思います。非法学部非経済学部かつ正規での労働さらには特別区まで半年を切ったタイミングで0から勉強を始めた私よりまずい状況の方はそうそういないと思います。こんな状況の私をも、法島先生はじめEYEの先生方は合格に導いてくださいました。安心してついていってよいと思います。公務員試験は特に筆記は必ず報われると体感したので、毎日少しずつでも学習を進めてば未来は開けるはずです。応援しています。
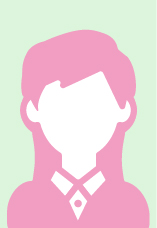
働きながらでも、公務員から公務員に転職できます!
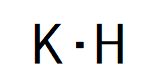
- 最終合格
- 東京都Ⅰ類B(一般方式)
より業務の幅が広く、影響力の大きい自治体で挑戦したい
私は2つの理由で公務員を目指しました。1つ目は、街づくりに携わる仕事がしたかったからです。2つ目は、女性が長く働き続け、活躍できる環境が整っているからです。
以上の理由で、新卒から約2年間市役所で勤務していました。少しずつ仕事に慣れてきた時に、より業務の幅が広く、影響力の大きい自治体で挑戦したいと思い、転職を考えました。
少人数制でいつでも相談しやすい環境が整っていたから
働きながらの受験であったことや、前職はSPI型試験で受験したため、公務員試験に関する知識がなかったことから、独学ではなく効率的に勉強を進められる予備校に通うことを決めました。
その中でもEYEに入学をした理由は2つあります。
1つ目は、少人数制でいつでも相談しやすい環境が整っていたからです。予備校に頻繁に足を運ぶことが難しかったため、ラインや電話を用いて気軽に相談できる点に魅力を感じました。
2つ目は、初回の面談時に岡田先生が丁寧に公務員試験の仕組みや勉強の進め方を教えて下さり、安心して学習できる環境だと考えたからです。
担任の岡田先生や千葉先生に気軽に相談できる環境が整っていた
1つ目は、学習で不安なことや分からないことがあった際に、担任の岡田先生や千葉先生に気軽に相談できる環境が整っていたことです。働きながらの受験ということもあり、困った時や悩んだ時に、校舎に行かなくてもすぐに相談できたことは、すごく心強かったです。
2つ目は、合格チューターの方に相談する機会や、他の受講生の方と交流する機会が多くあり、モチベーションの維持に繋げられたことです。
いかに勉強時間を確保し、効率的に勉強を進めるか
いかに勉強時間を確保し、効率的に勉強を進めるかということを第一に考えていました。そのため、まず過去問を見て傾向を掴むようにしました。
その後、科目ごとに得意不得意を分け、勉強の進め方を考えました。
私は、過去問で多くの割合を占めていた数的処理に苦手意識があったため、最も時間をかけて基礎から勉強しました。
人文科学や自然科学等の暗記科目は、時間が確保できなかったため、基本的には講義を受講せず、ダーウィンや解きまくりを繰り返し解き、暗記しました。
専門記述と小論文の対策は年明けから始めましたが、その他の暗記科目と並行しながら、論点の暗記や政策の研究をしなければならなかったため、結果的に焦りながら勉強することになってしまいました。そのため、もう少し早い時期からコツコツと進めれば、余裕を持って取り組むことができたなと思いました。
頑張っている自分を褒めながら、コツコツと継続することが大切
公務員試験は、長く辛くなることもあると思いますが、頑張っている自分を褒めながら、コツコツと継続することが大切だと思います。
仕事をしながらの勉強という中でも何とか乗り越えられたので、目標を叶えるという強い気持ちに向かって行動し続ければ、必ず合格できると思います。最後まで自分のペースで、無理せず頑張ってください。応援しています。

既卒生でも独力すれば必ず合格できる!
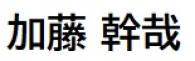
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類
区民と直接仕事ができる特別区に興味を持ち、目指すようになりました!
私が公務員を志望した理由は、安心して長く転勤もなく働けることと、幅広い人々の生活を支えたいと思ったからです。その中で、友人の勧めや区民と直接仕事ができる特別区に興味を持ち、目指すようになりました。
一番面倒見がよく、先生に相談しやすい環境が整っている
いろいろな予備校を調べていく中で、一番面倒見がよく、先生に相談しやすい環境が整っていると率直に思ったので、EYEを選びました。
DVDを使った授業は何度も再生することで、頭にインプット!
EYEで勉強していく中で、不安に思う事や分からないことがあったら、すぐに相談できるところがよかったと思います。また、DVDを使った授業だったので、理解できないところや聞き流してしまったところなど、何度も再生することで、頭にインプットすることができ、理解度が格段に上がりました。
私の学習の流れ
9月から12月にかけてのスタート期は、数的処理や判断推理を中心にやっていました。私は働きながら勉強していたので、朝に4,5問解くというのをほぼ毎日欠かさず行っていました。行きや帰りの電車の中では、憲法や民法、行政法などの法律科目をやっていました。また、ミクロやマクロなどの経済科目は、難しい問題はやらず、基礎的な問題をスーパー過去問で週に3~4日勉強しました。
1月から3月の中間期は、判断推理や数的処理を毎日やりながら、スーパー過去問を中心に学科系の科目に取り掛かりました。また、2月からは小論文講座を受講し、小論文対策をしました。また、特別区では過去に同じような問題が出題される傾向が強いと聞いていたので、年明けぐらいからEYEにお願いして、約15年分の過去問をやりました。
直前期は時事問題や社会科学、自然科学の勉強をしました。また、小論文は毎日、目は通していました。判断推理や数的処理もやっていました。
面接・小論文対策
小論文は2月からのEYEでの直前対策講座を受講し、特別区での小論文の書き方や頻出テーマに対する対応の仕方を勉強しました。その中で、10テーマほど暗記する必要があったので、どのテーマが来ても問題ない型や取り組みを覚えて、暗記しました。
私の面接対策・論文対策
面接対策では、5月の筆記試験が終わった2週間後ぐらいから取り掛かりました。自己分析などは、新卒の時にやっていたので、「なぜ公務員なのか」「なぜ特別区なのか」「公務員になって、何をしたいのか」などを徹底的に自分で用意した面接ノートに書きました。公務員になって、何をしたいのかを深掘りしていき、誰が聞いても納得してもらえるように落とし込みました。自分は子育て支援をやりたかったので、区のTwitterをフォローして、どのようなことをしているのかを調べたり、ネットで特別区の政策を覚えました。次に職歴があるので、学生時代のエピソードよりも現職で特に頑張ったことや学んだことを中心に面接ノートに書いていきました。また、特別区は面接冒頭に行われる3分間プレゼンが重要になってくるので、自分で言う原稿が決まったら、毎日練習していました。1次試験の合格の後は、既卒生の何人かと面接対策をしたり、人事院面接の前に1回模擬面接を行いました。この模擬面接は緊張感の中でやらせてもらえたので、良い練習になりました。
効率且つ計画的に、広く浅く勉強すること
試験科目が多く、仕事をしながらだったので、全部やみくもに勉強するのでなく、重点的にやる科目(数的処理、判断推理、民法、憲法、ミクロ、マクロ、小論文)などは多くの時間を割くようにして、効率且つ計画的に勉強しました。また、なるべく捨て科目は作らないように、広く浅く勉強することも心掛けました。
岡田先生や周りの人に頼ってください!
既卒生は新卒よりも、内定を取るのが難しいなどと言った噂が流れていますが、全くそんなことは無いと感じました。なので、最後まで諦めず、公務員になりたいという強い気持ちさえあれば、必ず合格できると思います。公務員試験はとても長丁場なので、不安に感じることがあると思いますが、その時は、EYEの岡田先生や周りの人に頼ってください。必ず解決してくれます。

再チャレンジ成功
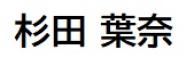
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類(衛生監視)
将来働くうえでもっと趣味や休息の時間を増やしたい!
私が公務員を志望した理由は、プライベートを大切にする働き方ができると思ったからです。前職は、病院の婦人科で胚培養士という仕事をしていました。不妊治療をする夫婦に貢献できるやりがいのある仕事でしたが、週6日の勤務や、残業が多くあったことから体調を崩し、休職をしました。休職期間中に将来働く上でもっと趣味や休息の時間を増やしたいと考え、公務員を志望しました。
EYEに決めた理由
池袋の校舎が家から通いやすかったのと、岡田先生が優しそうだったので決めました。
1年目の受験と2年目の勉強法
24歳の秋頃から勉強を始めました。一年目の受験では、冬ごろまでに教養の講義を全部見終えて、その後論文対策や専門試験の勉強をしていました。二年目は知識を維持するため、満遍なく勉強するようにしました。
様々な受講生と交流をし、情報交換ができたことがよかった
同じ受験区分の人や、既卒の人、大学生の人など様々な受験生と交流をし、情報交換ができたことがよかったです。衛生監視に合格した先輩を紹介してもらうことができたので、相談をすることができました。
私の面接対策・論文対策
面接対策
仕事が終わった後、約束をして既卒の受験生と面接対策をしました。また、岡田先生、法島先生に何度も面接対策をしてもらいました。
論文対策
講義を受けて書き方を学び、その後定期的に論文を書いていました。私は30分の科目質問を利用し、岩城先生に添削していただいていました。
科目質問を利用することで効率よく勉強
勉強のモチベーションを上げるため、科目質問を利用していました。科目質問の予定日までに論文を書くことや問題を解くことの目標を設定し、書いた論文の添削をしてもらったり、わからない問題の質問をしたりするようにしていました。仕事をしていたので勉強の時間を多く取ることができず焦っていましたが、科目質問を利用することで効率よく勉強ができたと思います。
相談できる先生や先輩、友人がいたことが勉強を続けられた理由です!
私は、EYEに二年間お世話になりました。一年目の受験で全ての受験先が不合格だった時は本当に悔しかったです。今でも当時のことを思い出すと悔しくて涙が出ます。もう一年勉強して受かる自信もなかったので本当は受験をやめたかったけど、意地で勉強を続けました。モチベーションとしては常にギリギリの状態でしたが、EYEに相談できる先生や先輩や友人がいたことが勉強を続けられた理由です。特に岩城先生には、勉強以外に悩んでいることや進路についても相談をしていました。甘やかしてはくれませんでしたが、アドバイスをくれたり一緒に悩んでくれたりして勇気付けられました。とても面白い先生なので、是非質問のついでにお話ししてみてください。
最後になりますが、体調に気をつけて勉強頑張ってください。EYEの先生やスタッフの方は親身になって相談に乗ってくれるので辛いことがあれば誰かに話してみてください。応援しています!

仕事と両立しての合格
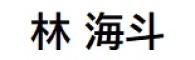
- 最終合格
- 特別区Ⅰ類、国家一般職
収入が安定、且つワークライフバランスがしっかり確保
私が公務員を志望した理由は、今の仕事で公務員の方と接する機会があり、そこで公務員としての業務の魅力に惹かれたからです。また、今後のためにも収入が安定していてかつワークライフバランスがしっかり確保できる仕事に就きたいと考え、公務員になることを決意しました。
既卒者の受講生数・合格者の多さが決め手
最初は大手の予備校の説明会や相談会に参加しましたが、あまり既卒者向けの雰囲気が感じられずにいました。その中で、EYEという予備校を知り、東京校の法島先生との最初の個別相談の中で、既卒者の受講生数・合格者の多さが決め手となり、EYEに入学しました。
私の学習の流れ
スタート時期(4~6月)
数的処理と文章理解は毎日決めた問題数以上を必ずこなすようにしました。仕事の都合上、WEB動画受講で、配信されたらすぐ消化することを心がけました。この頃は平日は3時間、休日は8時間くらい勉強していました。
中間期(7~12月)
見終わった講義は忘れないようにレジュメの確認テストや問題集をこまめに解いて確認します。過去問にも手を出し始めて、だんだん問題のクセや傾向を掴みながら解けるようになりました。受験先に合わせて、出やすいテーマ、◯年おきに出るテーマ、全く出ないテーマなど調べ、力を入れるべきところとそうでないところにメリハリをつけて学習していきます。この頃は平日は5〜6時間、休日は8〜10時間くらい勉強していました。
直前期(1月~)
論文に手をつけて、その他は過去問を何回も繰り返していました。
本番まで平日は以下のスケジュールで勉強していました。
7:00-9:00 数的・文章理解
9:00-9:50 通勤時間 法律科目参考書
14:00-15:00 昼休憩 学系科目参考書
20:00-22:00 自習室 経済系参考書
22:00-23:00 通勤時間 法律科目参考書
23:00-24:00 小論文・時事・自治体研究、一日の振り返り
この頃は平日は8時間、休日は10時間以上勉強していました。
情報収集!モチベーション維持!面接仲間ができた!
①先生との距離が近いということ、②面接仲間ができたこと、③情報収集に困らない、の3つです。ホームルームやイベントが毎月のようにあり、情報収集、モチベーション維持、仲間づくりに繋がりました。また、学習実績表を毎週先生に提出してアドバイスを頂いたり、いつでもLINEを通じて相談ができました。
私の面接対策・論文対策
面接対策
法島先生との個別相談や面接カード添削で何度も確認していただきました。
また、特別区一次合格者の説明会時に、既卒社会人メンバーが集まって練習しましょうという流れになりました。会社の終わりに喫茶店やカラオケ、EYEに集まって練習を何度も重ねました。筆記後から、EYEで教室開放をしており、大学生の方とも何度も練習しました。
論文対策
2月頃から準備を始めました。EYEの特別論文講義を受けて、それをもとに論文の構成を考えました。10テーマほど用意して添削をしたり、時間内に書き切る練習を重ねました。 毎日、時事・論文対策として日経新聞や自治体のHP、広報誌、情報サイトを確認し、最新の数字やデータをこまめに確認していました。
会社近くに自習室を借りました
①集中できる環境を作ること、②記録を毎日つける、この2つです。
まず、学生よりも可処分時間が圧倒的に少ないので、仕事と睡眠時間以外の時間をすべて勉強に当てる必要があります。集中して勉強するために、会社近くに自習室を借りました。
また、一日の終りに学習実績表を必ずつけました。進捗確認のため、1日を振り返る時間は必要だと思います。
苦しくても踏ん張れるかどうかが鍵だと思います
仕事を続けながら公務員受験をする場合は、覚悟を決めてください。飲みに誘われても断って、残業が多くて疲れても、問題集を開いて1問でも多く解いてください。眠いけどあと少し、疲れたけどあともう1問、そんな積み重ねが、必ず結果に繋がります。公務員受験は非常に長い道のりですが、先生や合格チューター、出会った受験仲間と一緒に乗り越えて行ってください。苦しくても踏ん張れるかどうかが鍵だと思います。応援しています。

地道に自分のペースで合格!
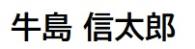
- 最終合格
- 国家一般職、埼玉県上級
父のように国の為になる仕事がしたい!
私が公務員を志望した理由としては、安定志向であったことも理由の一つなのですが、父が国家公務員であったこともあり、私も父のように国の為になる仕事がしたいと思い、公務員を志望しました。
手厚いサポートと受講生同士の交流の機会に恵まれている
公務員としての勉強を始めるにあたって、様々な予備校の説明会や体験授業を受けたのですが、最大の決め手となったのが手厚いサポートと受講生同士の交流の機会に恵まれているところです。公務員試験を受けるにあたって、受験科目の多さと約1年の勉強に耐えなければならなかったので、勉強も大変なのですが、何よりモチベーションの維持が難しいと感じました。そこで、EYEであれば、各校の担任の先生への個別相談や、学習計画表の記載により、誤った勉強をしている場合、すぐに適切な勉強に修正してもらえるところが大きな魅力だと思いました。
私の学習の流れ
スタート時期
最初はバランスの良い勉強を心掛けました。判断推理は好きな科目なので1日に3問、数的は1問、憲法は2問、文章理解は1問というように満遍なく勉強することを心掛けていました。
中間期
大体9月10月になると、夏休みまでに取り組んだ、判断推理や憲法、経済の基礎が固まり、ダーウィンから参考書を変えていました。11月あたりから、行政法、行政学が始まってくるので、それまで、世界史や日本史といった公務員試験における点数配分の少ない箇所の勉強をある程度していました。
直前期
参考書は過去問500以外には購入せず、基本的に今まで取り組んだ参考書で間違っていた箇所をひたすら復習することに専念していました。過去問500で間違えた範囲を把握し、それに該当する箇所を参考書で復習するといったことを行っていました。
すごい受講生はどのくらいできるのかとランキングで知り、より勉強に力が入りました
面接対策の講義や、グループワークがある授業が多いため、生講義に参加した際に声をかけられることがあり、受験仲間が作りやすかったです。他にも科目別の終了テストで、成績上位者はランキングで掲示されるので、自分よりすごい受験生はどのくらいできるのかということも知ることが出来、より勉強に力が入りました。
私の面接対策・論文対策
面接対策
生講義やイベントで知り合った友達と自分達で練習したり、個別授業の枠を消費して先生に対策してもらいました。あとは、チューターゼミに参加し、過去に合格された先輩方の意見を聞いたりしていました。
論文対策
直前対策講座で、既に完成された小論文のレジュメをもらうのですが、その内容をひたすら暗記していました。しかし、一言一句覚えるのではなく、キーワードとなる単語をちゃんと把握し、その単語をどのように繋げるのかについて考えながら覚えていました。
私生活をかなり早い段階からルーティン化
スタート時期から、直前期まで常にノンストレスで勉強することを心掛けていました。私自身、追い込みの勉強が得意でなく、ストレスを抱えすぎると何も手につかなくなってしまうので、私生活をかなり早い時期からルーティン化し、勉強はするのは当然なのですが、自分の趣味の時間も忘れないようにしました。
必ずあなたを必要とする人や組織は存在します!
公務員試験は本当に長丁場で、一年勉強しても面接で落ちたらどうしようという不安は私にも常にありました。実際に私も受験先の筆記試験や面接でかなり落とされてしまったのですが、必ずあなたを必要とする人や組織は存在します。それは志望先であるかは分かりませんが、最後まであきらめずに頑張ってください。

勉強で人生は変えられる
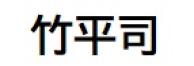
- 最終合格
- 千葉県上級(薬剤師)、富山県(薬剤師)
医療体制の整備と医療機関への行政支援をしていきたい!
私が公務員を志望した理由は、前職では専門職として働いていましたが安全な医療体制の整備と医療機関への行政支援をしていきたいと思い公務員を志望しました。
先生に相談しやすい環境、既卒向けのイベントがあることも決め手
再チャレンジをするにあたり、担任の先生に相談をしやすい環境を探していたところEYEの存在を知りました。また、既卒の受験生が多く、既卒向けのイベントがあることも決め手となりました。
EYEで学習して良かったこと
何度でも映像学習で見直しができること
私の学習の流れ
スタート時期:10月
再々チャレンジするにあたって、担任の法島先生と落ちた原因について一緒に分析しました。勉強時間配分を苦手な教科に多めに割いて、取り組みました。また、苦手な数的処理、憲法の動画を一から見直し始めました。そして、担任の先生に勉強の状況を毎週報告しました。
中間期:12月~1月
講義動画の消化と一般教養、専門教科(薬学系・化学系・衛生系)の過去問(8年分)を取り組みました。出来なかった分野を参考書(過去問解きまくり)の類似部分を復習してから、再度過去問に取り組みました。専門分野は、青本(薬剤師国家試験参考書)、参考書、管理栄養士の教本で取り組みました。過去の経験から、自分に合った1冊の問題集を繰り返して解くことを意識しました。
直前期:2月~5月
国家一般化学、食品衛生監視員の過去問を中心に取り組みました。過去問は、5周しました。解けなかった問題をコピーして、切り抜き、ノートにまとめました。出勤前の勉強時間に、前日と5日前に解けなかった問題を解いて復習していました。数的処理が致命的に苦手だった私が短期間で点数を伸ばせたのは、同じ問題集を繰り返して解いたからだと思います。
私の面接対策・論文対策
面接対策は、10月から取り組みました。担任の先生との分析で、面接での応対が苦手であること、回答の内容の正確さが足りなかったことが落ちた要因とされたので、担任の法島先生と週1の勉強状況報告時に練習しました。また、東京仕事センターも利用して対策しました。
小論文対策は、2つ行いました。1つ目は、参考書のテーマ全部を準備しました。また、各テーマの数字のデータを常に更新することに努めました。2つ目は、通勤中に非公開設定にしたSNSに書き込み練習しました。職場のお昼休みに、朝書いた文章の整合性をチェックし、模範解答と比較しました。
毎週の報告の際に「できなかった」ことを中心に相談しました
勉強で工夫したことは、時間の管理と勉強の報告を毎回行うことです。解答時間を意識するためにキッチンタイマーを用いて勉強していました。また、悩むときや考えるときも意識的に使いました。勉強の開始、終了の報告をSNSや法島先生のLineアカウントに行うことも意識的に行いました。また、毎週の報告の際にも「できた」ことより「できなかった」ことを中心に相談しました。
最後まで戦い続けることでやり遂げることができました
私は、社会人の再々チャンレジで合格できたのは、最後まで面倒を見てくれた法島先生をはじめとするEYEの先生方や同じ目標をもつ仲間の存在が大きいです。苦しい時期が続きましたが、たくさん先生方に相談し、自分を信じで最後まで戦い続けることでやり遂げることができました。

1年越しのリベンジ合格!
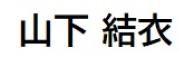
- 最終合格
- さいたま市(大学卒業程度)、国立大学法人等職員
人に寄り添って職務ができる公務員のほうが私に合っている!
私が公務員を志望した理由は、利益を追求する民間企業よりも人に寄り添って職務ができる公務員の方が私に合っていると思ったからです。
自分に合っていて頑張れそうだと思った
説明会での受講生の雰囲気と体験授業を受けた感じが自分に合っていて頑張れそうだと思い、EYEに決めました。
私の学習の流れ
・スタート時期(大学2年2月~浪人7月)
大学2年の2月に入校し、生講義に3回ほど参加しましたが、緊急事態宣言が出て通うことが難しくなりました。3年は公務員試験の勉強がほとんどできなかったため、12月頃に岡田先生に相談した上で、浪人することも視野に入れ始めました。4年で練習も兼ねて模試感覚で3つ受験しましたが、筆記試験ですべて不合格となってしまったので、そこからは次の年に向けた勉強を始めました。具体的には、4年の4~6月に数的処理、文章理解を勉強し、不合格後の7月からはミクロの勉強を始めました。
・中間期(浪人8月~12月)
この時期はマクロ、民法、憲法の勉強を始めました。マクロは途中で心が折れかけたので、前半部分しか勉強していません。民法も苦手だったので、この時期は思うように勉強が進まず、かなり苦しかったです。
・直前期(浪人1月~)
1月に行政法、2月に行政学、政治学、社会学、3月に財政学、経営学、4月に生物、化学、時事、5月に会計学、簿記の勉強を始めました。法律科目がかなり苦手だったので、他の科目で得点を稼ごうと思い、法律科目は最低限の勉強しかしていません。数的処理は得意な科目だったので毎日少しずつ過去問を解くだけにして、残りの時間は他の科目にあてていました。6月に入ってからはほとんど筆記試験の勉強はしていません。
先生方との距離感やレジュメが分かりやすいところが自分に合っていた!
やはり、アットホームなところだと思います。面接アドバイス会で初対面の受講生が話しかけてくれたり、先生方に相談しやすい環境であったりして、とても救われました。何か悩んでいることがあれば、些細なことでもすぐに岡田先生にLINEで相談していました。先生方との距離が近いEYEだからこそだと感じています。また、個人的には授業やレジュメがわかりやすく、自分に合っていたなと思っています。
私の面接対策・論文対策
・面接対策
面接対策は6月中旬頃から始めました。面接情報シートに書いてある質問や面接アドバイス会でもらえる想定質問集を見て、それに対する自分の答えをWordにまとめ、それを岡田先生との面談で確認してもらいました。答えを覚えたり、自分で答える練習をしたりして対策していました。
・論文対策
2月に入ってから小論文の講義を見て、岡田先生のHRで教えてもらえる特別区の予想10論点と特別区の模試で出た論点の小論文を作成し、個別授業や科目質問などで添削してもらいました。添削は3月中旬くらいまでに全て終わらせましたが、この時期は科目質問の予約が埋まっていることもあったので、1月くらいから始めればよかったと思いました。岩城先生に添削してもらいましたが、直すべきところはもちろん、良い点も教えてくれたのでモチベーションも上がりました!
自分で勉強ペースの目標を立てるのはおススメです!
勉強ペースが遅めだったこともありますが、頑張ってもできそうにない範囲は無理しないことも大切だと思います。その分、得意科目ではあまり点を落とさないように気をつけていました。また、月ごと・日ごとのチェックリストを作ることで、進捗状況が目に見えてわかるのでモチベーションになっていました。自分で勉強ペースの目標を立てるのはオススメです!
もう一度気持ちを切り替えて頑張りましょう!
浪人することはかなり悩んだ上で覚悟を決めて決断したつもりでしたが、周りの友人が社会人になっていく中、自分だけ勉強をしなければならない状況にやっぱり焦りを感じたり、落ち込んだりすることもありました。不合格をもらう度に今年も全部不合格だったらどうしようと不安にもなりました。それでも、自分を信じて突き進み、最終的に第一志望の合格をつかみ取ることができました。新卒の方も私と同じような状況の方も、周りの人と自分を比べすぎずに自分のペースで最後まで頑張ってほしいと思います。不安に押しつぶされそうになっている人もいると思いますが、過ぎたことや終わったことはいったん忘れて、もう一度気持ちを切り替えて頑張りましょう!

継続は力なり!
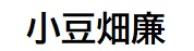
- 最終合格
- 国税専門官、国家一般職
年齢に関係なく内定を勝ち取れる点に魅力!
建前:面接などでは、国家公務員として働いている部活の先輩に憧れて公務員を目指したと伝えていました。 本音:実際のところは、民間企業の営業職が私には向いていないと思ったこと年齢に関係なく内定を勝ち取れる点に魅力を感じ公務員を志望しました。
そのため、大学を卒業してから1年半経過していても内定を頂くことができました。
決め手は自習室です!!
決め手は自習室です。私は家では全く勉強ができませんし、しません。そう心に誓っています。その代わり、何か予定がない限り毎日予備校に通い、開館時間から閉館時間まで自習室で勉強をするという「覚悟」をもって取り組んでいました。そのため、集中できる環境が整った自習室が私の予備校選びの基準でした。具体的には、パーテーションが備わっているか、ラウンジからの声や雑音が聞こえないか、直前期に自習室を利用する人が増えても席に余裕がある席数かどうか等です。そのような中で、私は渋谷本校を利用していたのですが、渋谷本校の自習室は、私の中の要件をほとんど満たしていたので、EYEを選びました。
受験仲間がいなければ最終合格することはできなかった!
受験仲間を作るきっかけや機会を多く提供してくれる点です。公務員試験では受験に関する情報や面接練習がかなり重要であると思っています。そういった意味で、仲間の存在はとても重要になります。私も二人だけ受験仲間を作ることができましたが、私の知らない情報を持っていたり、面接練習の相手になってくれたりと、この二人がいなければ最終合格することはできなかったと思っています。
私の学習の流れ
私は大学を卒業して4月1日から学習を始めました。大学を卒業していたこともあり、時間があったので開校している日は毎日開館から閉館まで自習室で学習していました。 流れとしては、復習に力を入れて1月までに憲法民法ミクロマクロ判断数的等の主要科目の講義を終わらせていました。1月から学系、人文科学の講義や論文対策を行いました。 面接対策は試験が一通り終わった頃に始めました。
私の面接対策・論文対策
まず論文対策については、参考書を入手しま、その後、1月末に岡田先生が特別区の論文テーマの出題予想をしてくださるので、そのテーマの模範論文を丸暗記します。これだけで、特別区以外の論文も攻略できます。私は特別区、国家一般職、国税専門官、横浜市を受験しました、すべて一次合格することができました。
面接対策については、EYEで知り合った友人と面接練習を3回ほど行いました。ただEYEの先輩では、一回も面接練習を行わずに国家一般職で内定を勝ち取っている人もいるので人によります。私は三回では少なかったと後悔しています。
学系は絶対にやったほうがいい!
勉強のやり方としては、講義を受けた後、復習を3回行った後に次の講義を受けるようにしていました。講義をすべて受け終わる2月頃まで基本的にはこのやり方でやっていました。ただ、このやり方は時間がある人向けです。1月からは、毎日論文の暗記と学系のレジュメに目を通すことを欠かさずに行っていました。
アドバイスとしては、学系は絶対にやったほうがいいと私は思います。私も先輩から学系をやったほうがいいと言われて勉強し始めたのですが、学系が私の得点源になりました。少ない時間で結果が出るのでとてもコスパが良い科目といえます。
質よりも量!フリーターが不利にはならない!
私は他の人よりも要領が悪いので、質よりも量を重視していました。そのため、閉館日以外は毎日自習室で開館から閉館まで勉強をしていました。この勉強方法は私にしかできないものだと思っています。なので、この合格体験記を読んでいるあなたも、自分に合った勉強法を見つけて頑張ってください。
ちなみに私は大学を卒業してからフリーターとして1年以上勉強をして内定を勝ち取ることができました。なので、フリーターが不利にはならないので、諦めずに頑張ってください。

「民間企業経験1年半」、「9月下旬スタート」でも合格できる!
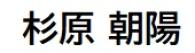
- 最終合格
- 国税専門官、国家一般職
改めて公務員を目指したいという思いが強くなった!
大学在籍時に公務員を目指していました。しかし、当時は勉強が思うように結果が出なかったのと、周りが早期に民間企業の内定を取っていたことに焦ってしまったことから、公務員試験に失敗し、民間企業に就職しました。その後、職務を通じて、改めて公務員を目指したいという思いが強くなったため、再度公務員受験をすることを決めました。
入校前にも関わらず丁寧な対応
インターネットで予備校を調べていたときにEYEを見つけました。面倒見のよさそうな予備校だと感じ、気になったので、zoomで法島先生から詳細を聞きました。そこで、既卒生が多いことや手厚いサポートを受けられることを知りました。また、入校前にも関わらず、既卒ゼミに参加させていただき、とても丁寧な対応をしていただいたので、EYEに入校を決めました。
疑問や悩みなど相談しやすかった!
先生と生徒の距離が近いため、疑問や悩みなど相談しやすかったことが良かったと思います。
私の学習の流れ
スタート期(9~11月)
前職は9月末で退職していたため、時間はありました。また、9月の下旬に入校し、周りよりも遅いスタートとなったため、4月生の進捗状況に追いつきたいと思い、法島先生に教えていただいた進め方を基に1日に2本の授業を見ました。授業で使用したレジュメを読み込むことに注力し、その後にダーウィンを解くというようにして基礎的な知識を定着できるよう取り組みました。特にミクロマクロが難しいと感じていたため、その2教科は力を入れました。数的処理、文章理解については時期関係なく毎日解くようにしました。
中間期(12~3月)
12月の初旬の頃には授業の進捗状況にも余裕ができたので、1日1本の授業を見るという進め方に変えました。12月までの学習内容はスタート期と同じ内容でしたが、1月からは、参考書を購入し、実践問題を解くことを中心に、分からない分野があればレジュメに立ち返るという勉強方法に変え、学系教科(社会学、経営学等)や教養科目にも本格的に取り組みました。また、2月から論文にも取り組むと同時に、通常授業とは別に直前講座が開催されていたため、すべての講座に参加しました。
直前期(4月~)
全教科の参考書の問題にひたすら取り組みました。また参考書の進め方については、一番日程の早い試験の頻出度が高いもの(星2つ以上)だけを解き、頻出度の低いものは軽く見るようにしていました。また、過去問につきましては、国家一般職以外は1回も解かなかったので、1回でも取り組めば良かったかなと思います。
私の面接対策・論文対策
面接対策
対策を始めたのが12月で、5月下旬ごろから本格的に取り組みました。自己分析を行なうことや面接でよく聞かれることをまとめ、自分の言葉で説明できるようにしました。そして、合格チューターゼミや6月頃から始まった生徒同士での面接練習などEYEで行われているイベントに積極的に参加し、「人前で言いたいことを話す」ということができるように面接練習の数をこなしました。7月からは仕事センターにも行き、職員を相手により緊張感のある面接練習をすることも始めました。もともと面接は苦手でしたが、面接回数をこなすことや自己分析を徹底して行うことにより、面接に対し自信を持つことができたと思います。
論文対策
2月から対策を始めました。正直、論文対策の本を見ても、何をどうすればよいか全くわかりませんでした。しかし、直前講座の一つである「吉井先生の論文道場」を受講してから、どのような構成で書けばよいか、どのような言葉遣いが適切なのかなどを理解できるようになりました。基本的に、あらかじめ作成されている論文を基に、自分なりに言葉や具体例を変え、論文を作成しました。特別区についてはEYEの先生や吉井先生が予想した出題テーマから10テーマの論文を準備しました。
日曜日は基本的に勉強を休む日にして気が向けば勉強する
EYEが開いている日は朝からEYEへ行き、勉強することを習慣づけました。また、「日曜日は基本的に勉強を休む日にして気が向けば勉強する」ということや、「集中できない日は好きな教科だけ勉強する」というようにして、継続して勉強ができるように意識しました。そして、毎月1回面談を予約し、法島先生に進捗を報告することや疑問や悩みを話すことで、モチベーションの維持や学習管理を行いました。
周りの人よりも出遅れたが、それでも公務員試験に合格することができた!
大学卒業後に就職した民間企業を1年半で退職した経歴を持ち、かつ9月下旬から勉強を始めたため周りの人よりも出遅れましたが、それでも公務員試験に合格することができました。公務員試験は、周りに流されず、うまくいかないときでも諦めずに粘り強く取り組むことが大切だと思います。また、適度な息抜きも必要だと思うので、あまり自分を追い込みすぎず、最後まで諦めずに頑張ってください。
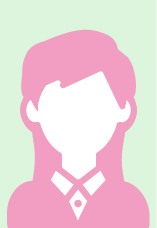
得意科目を極めて合格!
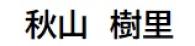
- 最終合格
- 千葉県上級
企業よりも公務員のほうが向いていると感じて進路変更!
私が公務員を志望した理由は、人や地域のために働きたいと考えたからです。大学3年の冬に就職活動をしていた際、企業よりも公務員の方が向いていると感じて進路変更をしました。進路を決めるのが遅かったため、就職を一年遅らせることにしましたが、EYEには既卒の人も多くいたので心強かったです。
勉強の進め方が明確に分かり、指針をもらいながら安心して通える
私がEYEに入学したきっかけは、公務員をしている母親の同僚にEYEを卒業された方がいて、その方に紹介していただいたことです。受講料やサポートの手厚さ、自身の経験などを含めておすすめしていただきました。また、担任の法島先生と面談をした際に、勉強の進め方が明確に分かり、指針をもらいながら安心して通えると感じました。
好きな時間に好きな場所でオンライン上で行えることがありがたかった!
面談や講義など、ほとんどをオンライン上で行えることです。私自身、一人で勉強するのが向いていると感じていたので、オンラインで講義を見られるのはありがたかったです。また、習い事やアルバイトと並行しながら勉強を頑張りたかったこともあり、好きな時間に好きな場所で、動画の早さも調節しながら講義を受けられたのはとても大きかったです。
私の学習の流れ
スタート時期
3月に入学してから秋くらいまでは、配信された講義を見ることがメインでした。数的や文章理解などの教養科目は自習も行っていましたが、ほとんどはとりあえず講義についていくことを意識してやっていました。
中間期
秋以降は少し教養科目の頻度を減らし、講義を受けつつ専門科目の暗記を自習で行うようになりました。自分が読みやすいと思う教材を使うのがいいと思います。過去問を解くほどのレベルに足していなかったため、インプットをメインに行い、問題集を使って確認するようにしていました。
直前期
4月くらいからは、過去問を解いてわからない問題があれば教材で復習するという形式をメインにやっていました。志望度が高い自治体の過去問は最新のものを購入するなどして、直近5年くらいの傾向はわかるまで解きました。教養科目の中でも暗記寄りの科目(歴史系や時事など)は、「光速マスター」や「速攻の時事」などの要点がまとまった本を使用し、いつでも確認できるように持ち歩いていました。
私の面接対策・論文対策
面接対策
誰よりも志望先への想いを語れるように意識していました。志望先のパンフレットを読み込んだり、を入れている政策をホームページで見つけたりして、面接カードやよくある質問に沿って回答を考えました。また、志望動機で取り組みたい仕事などがあれば、それに近い政策を探して語れるようになっておくように準備しました。
論文対策
論文対策の本を一冊購入し、講師の方との個人面談で予想論点を一緒に考え、それに沿って8個くらいまとめました。3回ほど実際に論文を書いて添削をしてもらい、書き出しや構成の作り方を覚えてからは、論点の暗記をメインに行っていました。
自分でもできそうな問題を探してやる方がいい!
直前期には、不安になることがあれば担任の先生や講師の方に質問することを意識しました。勉強に関しては、数的と理系科目が苦手だったため、落としてはいけない問題だけは取ることを意識し、あとは得意科目でカバーしていました。また、分からない問題に立ち向かうよりは、自分でもできそうな問題を探してやる方がいいと思います。本番に解けた方がいい大事な問題は先生に教えてもらい、繰り返し解くようにしていました。
諦めなければいい結果が出ると信じて!
不安になることがあると思いますが、担任の先生をはじめ、講師の方々が親身になってサポートしてくれるので安心して準備ができます。私自身、勉強が上手くいかない時期も多くありましたが、公務員になりたいという気持ちはなくならなかったので、最終的には頑張れたのだと思います。諦めなければいい結果が出ると信じて、頑張ってみてください。
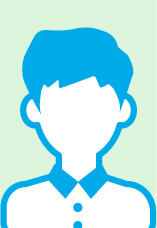
働きながらでも合格可能です
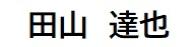
- 最終合格
- 茨城県(大学卒業程度)、特別区Ⅰ類
自分や大切に思う人の生活を豊かにできる
自分や大切に思う人の生活を豊かにできる点に公務員としての魅力を感じて志望しました。大学4年生時、去年と2度の公務員試験を受験しましたが合格することができず、今回、3度目の挑戦で合格することができました。
受験仲間を作るイベントが開催されているなどアットホームな環境
3度目の公務員試験に挑戦するために勉強のスケジュールをしっかりと立てること、相談できる相手や受験仲間が欲しいと思い予備校に通うことを決めました。予備校を選ぶ際にはいくつかの予備校の説明会や面談に参加しましたがEYEの法島先生の面談を受けた際に既卒者メインで担当されていることや受験仲間を作るイベントが開催されているなどアットホームな環境に魅力を感じEYEに入校することを決めました。
私の学習の流れ
スタート時期(11月~1月)
Webにて授業を消化していくこと、そして復習もしっかりやることを決め勉強をスタートしました。月水金に1本ずつ土日に3本、1週間で計6本の授業を消化していました。授業を観たあとにはすぐに復習に取り掛かれるスケジュールを組み、授業の復習は当日または翌日にはするようにしていました。休日であり、まとまった時間の取れる土日には1週間の総復習をやっていました。また、合格チューターの個別相談には積極的に参加し、そこで出会った合格チューターさんには筆記試験だけでなく面接練習の際にも色々とお世話になりました。
直前期(2月~4月)
2月中旬頃からは自主学習に多くの時間を割きました。一般的な受験生だと志望先の過去問もやっている頃だと思いますが基礎的な知識が身についていないと思ったため授業でやったことや市販の参考書を使って基礎的な知識の定着を目指して勉強を続けていました。3月に入り特別区、地方上級の過去問をやり始めましたが多くの時間はそれまでやってきた基礎知識の定着を目指した勉強を続けていました。
LINEを使って気軽に相談することができる
各校舎に担任の先生がおり、LINEを使って気軽に相談することができ、モチベーションの維持にも繋がりました。受験仲間を作るイベントが開催されている点もすごく良かったです。
私の面接対策・論文対策
面接
県庁の筆記試験が終了し、特別区の1次試験の合格発表後に本格的に取り掛かりました。
合格チューターでお世話になった方や特別区合格者説明会で知り合った既卒の受験生と仕事終わりや土日に練習していました。自分や受験仲間が練習する度に上達していることを感じることができたため数をこなすことの大切さを痛感しました。
論文
吉井先生の論文講座で受講した参考答案を土台として一部、自分の言葉に変えて書きやすい様に修正して暗記をしていました。また、テーマの中でも他のテーマでも使える汎用性の高いテーマを中心にやっていました。
最後まで基礎を勉強!何度も同じ問題をやっていました!
最後まで基礎を勉強したことです。特に苦手だった数的、それをカバーするための文章理解は勉強スタート時からほぼ毎日、解いていました。また、基礎問題を多くこなし、できた問題、できなかった問題、できたけど時間がかかった問題をノートにつけ、何度も繰り返し解けるようになるまで同じ問題をやっていました。
筆記試験を突破するだけの力は身につけることができます!
既卒者は大学生の受験生に比べると時間的に不利な状況にあると思いますがたとえ時間が少なくても継続的に勉強することで高得点は取れなくとも筆記試験を突破するだけの力は身につけることができます。継続は力なりです。私は恥ずかしながら大学4生時、去年とほとんどの自治体に筆記試験で落ちています。仕事をしながら残業の多い会社で働く私でも合格することができましたので皆様も最後まで諦める事なく何事も継続的にやることを意識して取り組んでみてください。

